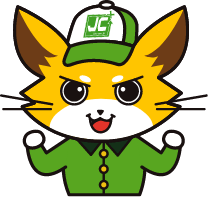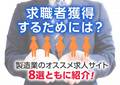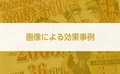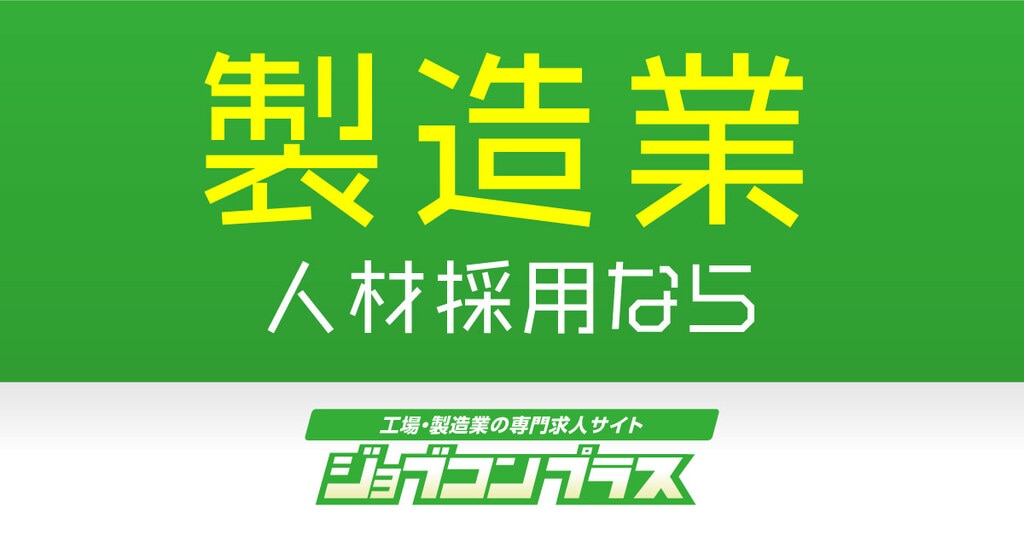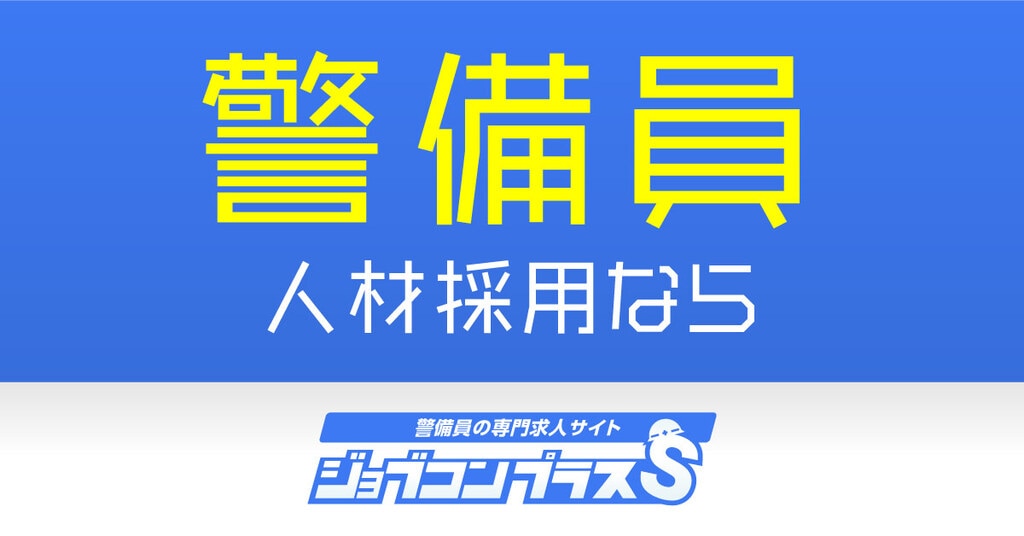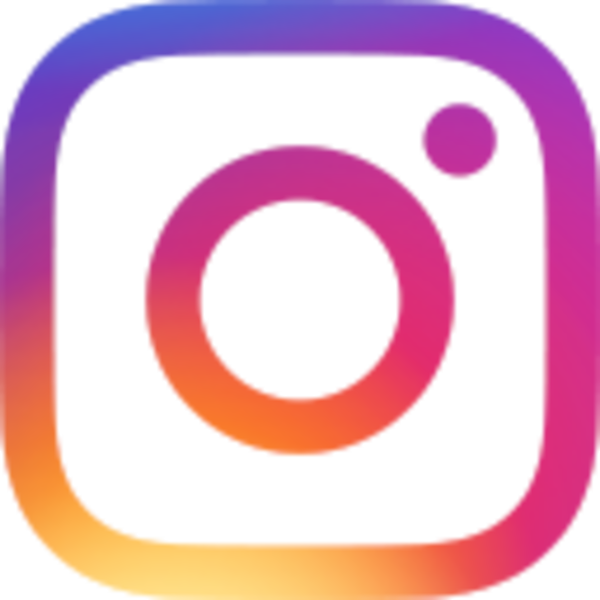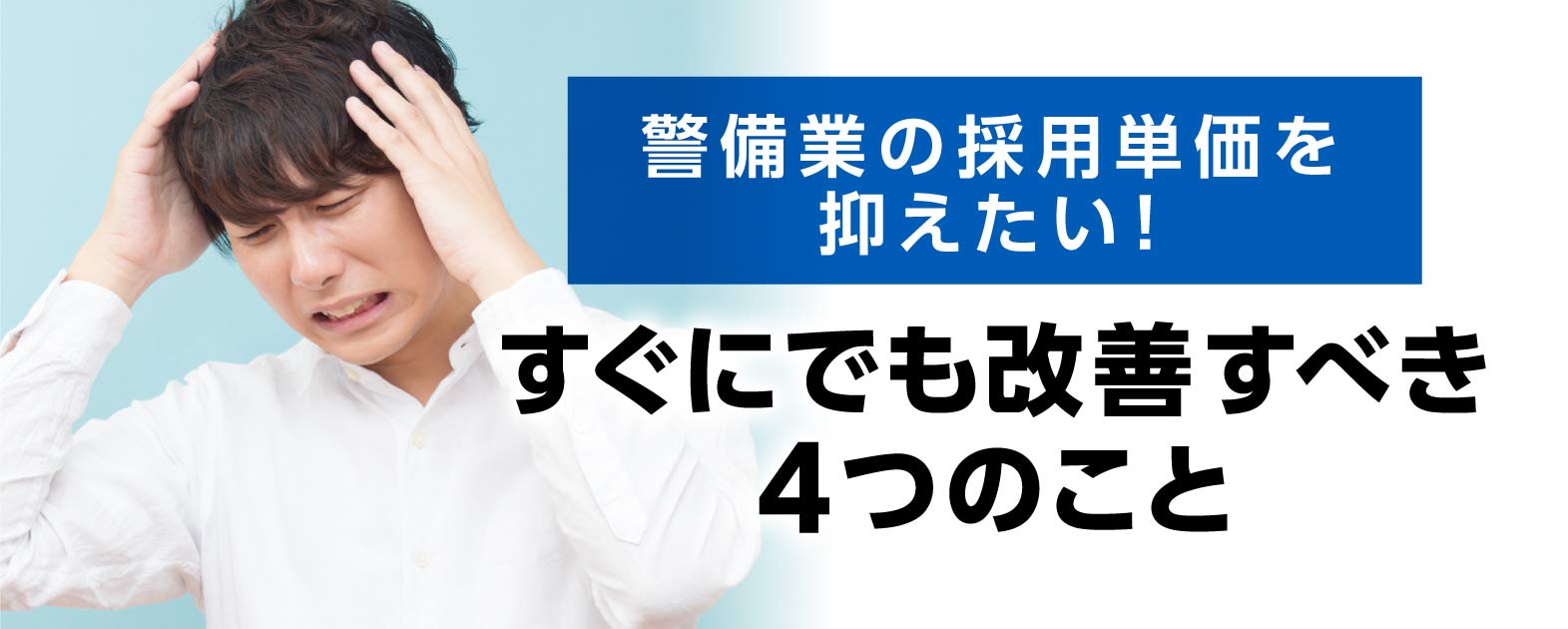
【繁忙期前に備えよう!】警備業の採用単価を抑えられる!すぐにでも改善すべき4つのこととは?
企業は、業務を担わせ利益を上げるために従業員を雇用します。
雇用の際に不可欠となるのが採用コストです。警備業、特に交通誘導警備は繁忙期と閑散期がありますが、繁忙期前にはコストをかけてでも採用を増やして十分な人材を確保しなければいけません。
しかし、利益を上げるためには採用単価を抑えて効率よく人材を確保する必要があるでしょう。
そのために企業が行うべき施策や意識すべき考え方を解説します。
目次[非表示]
- 1.採用単価は雇用形態や業界によって異なる
- 2.警備業は他業種と比べても採用単価が高め
- 3.警備業の採用単価が高いのはなぜ?
- 3.1.体力的負担の大きさ
- 3.2.不規則な勤務時間
- 3.3.高い離職率・早期離職
- 3.4.資格・研修が必要
- 4.警備業界の採用市場の現状と課題
- 4.1.有効求人倍率の高さ
- 4.2.若年層の応募減少
- 4.3.高齢化社会による人手不足
- 5.警備業の採用単価を抑えるために必要な4つのこと
- 5.1.採用ターゲットを明確にする
- 5.2.求人情報の掲載先を見直す
- 5.3.ターゲットに合わせて魅力をアピールする
- 5.4.働きやすさを可視化する
- 6.まとめ:採用単価の抑えどころを見極めよう
採用単価は雇用形態や業界によって異なる
採用コストは、業界や職種、さらには正社員・アルバイトなどの雇用形態によっても大きく異なります。同じ業界内でも、新卒・中途、正規・非正規といった条件の違いによって、採用にかかる費用は変動します。
ちなみに、採用コストの総額には求人掲載など外注にかかる費用だけではなく、企業内のスタッフが採用や人事のために行う業務にかかる費用なども含まれます。 実際に他の企業が採用のためにかけているコストは多くの採用担当者にとって気になるところでしょう。
就職みらい研究所の「就職白書2020」によれば、2019年度の新卒採用にかかる単価は93.6万円、中途採用にかかる単価は103.3万円だったというデータがあります。
非正規の採用コストに関してはどうでしょうか。株式会社マイナビが2022年に行った調査によると、アルバイトやパートの平均的な採用単価は、販売(コンビニ・スーパー)で5万8000円、飲食業(キッチン)で6万7000円、家庭講師・講師で4万6000円、介護で6万4000円となっています。
ブルーカラー業界では、製造ライン・加工(メーカー)で10万6000円、配達・配送で7万9000円、警備員の採用単価は7万4000円と、その他の業種よりも高くなっているのです。
採用単価は業種を問わず年々上昇しており、特にブルーカラー業界では「人が集まりにくい」「採用後の定着が難しい」といった課題に直面しています。
警備業は他業種と比べても採用単価が高め
警備業の採用単価は、アルバイト採用全体で見ると平均的ですが、正社員雇用に限ると、他のブルーカラー職種と比べて高くなる傾向があります。1人あたり約20万〜30万円程度が一般的とされ、製造業(15万〜20万円)やドライバー職(18万〜25万円)よりも高めです。
※出典:ディップ総合研究所、マイナビ、HR総研、エン・ジャパン調査などをもとにした概算値(2024年度〜2025年春時点)
警備業の採用単価が高いのはなぜ?
体力的負担の大きさ
警備の仕事は、炎天下での交通誘導や深夜帯の巡回業務など、身体に大きな負担がかかる場面が少なくありません。さらに、長時間の立ち仕事や、常に周囲の状況に気を配る必要があるため、精神的にも高い集中力と緊張感を求められる職種なので応募できる人材が自然と限られてしまう傾向にあります。
そのため、体力的な理由からも長期間の就業が難しく、離職率が上がりやすい傾向があります。
不規則な勤務時間
警備業は24時間体制の現場が多く、日勤・夜勤のシフト制や休日出勤など、勤務形態が不規則になりがちです。生活リズムが崩れやすく、身体的・精神的な負担も大きくなるため、継続的な勤務が難しい要因となります。
そのため、Wワーク希望者や家庭と両立したい人にとっては働きづらい環境となり、応募の母数が限られます。
高い離職率・早期離職
仕事内容の理解不足によるギャップや勤務環境の厳しさから、「とりあえず応募してみたけれど、すぐに辞めてしまう」というケースも少なくありません。
その結果、企業は短期間で繰り返し採用活動を行う必要があり、そのたびに求人広告費、面接対応、人材育成にかかる研修費用などが積み重なり、1人あたりの採用コストが増加する結果となります。
資格・研修が必要
警備業に就くためには、業務開始前に法定の新任研修(20時間以上)を受けることが義務付けられており、さらに交通誘導や施設警備など業務内容に応じた専門資格の取得が求められるケースもあります。
そのため、採用後すぐに即戦力として現場に立てるわけではなく、教育や資格取得のための時間的・金銭的な投資が発生します。また、研修を実施する側の人員確保やスケジュール調整も必要になるため、現場にも一定の負担がかかるのが実情です。
これらのように、1人採用するまでにかかる社内コストが高くなってしまう理由があります。
警備業界の採用市場の現状と課題
有効求人倍率の高さ
警備業を含むブルーカラー職種全体で有効求人倍率が上昇傾向にあり、1人の求職者に対して複数の求人が存在する状況が続いています。
厚生労働省のデータによると2024年6月時点で保安業の有効求人倍率は5.77倍で、全職業の平均1.23倍を大きく上回っています。
このような高倍率下では、待遇改善や広告出稿など人材確保に向けた取り組みが必要になり、その分採用単価が上がりやすくなる傾向にあります。
若年層の応募減少
警備の仕事は「きつい」「将来性が見えにくい」といったイメージが根強く、若年層からの応募が年々減少傾向にあります。20〜30代の人材が集まりにくいことで、採用活動が長期化し、結果としても時間とコストがかかる原因になっています。
高齢化社会による人手不足
現在の警備業界ではシニア層の活躍が目立つ一方で、年齢による体力的制限などから継続勤務が難しいケースが増えています。若手の補充も進まない中、人手不足が慢性化し、それに伴い採用コストがかさむ要因になっています。
このように、有効求人倍率の高さや若年層の応募減少、高齢化による人材不足といった外的要因が重なり、採用難が続いており、それに伴い採用単価も上昇傾向にあります。
警備業の採用単価を抑えるために必要な4つのこと
ここからは、警備業の採用単価を抑えるための考え方や施策について解説します。
採用ターゲットを明確にする
まずは、どのような人材が欲しいのかを明確にすることが、採用単価を抑える第一歩です。
若年層をターゲットにするのか、中高年層を中心に採用するのかによって、適切な求人媒体や訴求内容、働き方の設計は大きく変わります。
積極的に雇用したい年齢層や、どの業界・職種からの転職者を狙うのかなど、ターゲットを明確にすることが重要です。照準を絞り込むことができれば、そこにアプローチするための戦略を立てることができます。
たとえば、若年層を取り込みたい場合には、SNS広告やWEBで完結する応募導線(面接予約や日程調整をオンライン化)を活用することで、応募者の利便性を高めると同時に企業側の人件費も削減できます。
また、ターゲットの前職経験や求める働き方(フルタイム・副業・日払い希望など)を把握したうえで、訴求ポイントを絞り込むことが重要です。広告の掲載先や採用手法を再考し、無駄な出稿や対応を避けることで、効率的な採用活動が可能になります。
このように年代や性別、前職などを考慮して広告の掲載先や採用方法などを再考してみましょう。
求人情報の掲載先を見直す
求人情報をどの媒体に掲載するかも、採用単価に大きく影響します。
企業HPなどに採用ページを設けるのも一つの手段ですが、ゼロの状態から立ち上げるのであれば外注する方が初期費用を抑えやすいこともあります。
ただ、どの求人サイトでもよいわけではありません。
複数の求人サイトへ無差別に出稿することは、かえって「人が集まらない企業」というネガティブな印象を与えるリスクもあります。掲載媒体は、ターゲット層が多く利用しているかどうかを基準に、厳選することが大切です。
無料掲載が可能な媒体もありますが、利用者が少なかったり、露出が限定されていたりするケースも多く、効果が見込めないことも。また、無料のままでは上位に掲載されず多くの人の目に触れない可能性もあります。
コストを抑えたいのであれば、むしろ有料であっても、求職者に届く媒体を選ぶ方が、結果的に応募数増加と採用単価の低減につながります。
ターゲットに合わせて魅力をアピールする
求人情報には、ターゲットの属性や価値観に合わせた魅力を盛り込みアピールすることも欠かせません。
これまでの経歴により、求職者が持つスキルや転職先に求めることなどは変わります。また、年齢層や性別によっても応募先を選ぶポイントには違いが出てくるでしょう。
たとえば、40代であれば「家族で生活できるだけの賃金が稼げるか」に重点を置く人が多く、60代であれば、「身体に負担の少ない仕事」「自分のペースで働ける環境」を考慮して再就職先や転職先を選ぶ人もいるはずです。
警備員の場合、「まずはアルバイトからはじめて、自分に合っていると感じれば正社員を目指したい」「日払いや週払いで給与を受け取りたい」「すぐに働きたい」といったニーズを持つ人も多いため、こうした要望に対応できる制度があれば、求人票に記載しておくことが効果的です。
もし可能であれば、こうした層に対応できるような環境や制度を整えたうえで求人に記載してください。
ターゲットの要望に応えられる内容とともに、企業や警備業そのものの魅力を適切にアピールできれば応募者を増やせるでしょう。
応募者が「自分に合っている」と感じられる情報を伝えることで応募率が高まり、結果として採用単価の低減にもつながります。
働きやすさを可視化する
警備業は仕事内容のイメージが伝わりにくく、「きつそう」「夜勤が不安」といった先入観から応募をためらわれやすい職種です。
だからこそ、働く環境や実際の業務内容を具体的に伝える“見える化”が重要です。
たとえば例えば、「1日のスケジュール」や「現場の写真」「現場で働く社員の声」を掲載することで、仕事の流れや雰囲気が伝わり、安心感が生まれます。
また、「夜勤前に現場見学が可能」「週払い制度ありで急な出費にも対応」といった情報も、求職者の不安を解消し、応募率のアップにつながる要素です。
このように、“働きやすさ”を具体的に伝えることで他社求人と差別化でき、採用効率も向上します。
まとめ:採用単価の抑えどころを見極めよう
警備業は、有効求人倍率の高さや若年層の応募減少、高齢化による人手不足といった複数の課題を抱えており、採用単価が高騰しやすい業界です。
しかし、採用活動のやり方を見直し、「誰に、どう伝えるか」を明確にすれば、限られた予算でも効果的な採用は可能です。
「採用ターゲットを絞り、最適な媒体を選び、求職者が「ここなら働けそう」と感じる情報を届ける」
この基本を丁寧に徹底することで、採用の「精度」は格段に高まり、コストも自然と抑えられていきます。
特に重要なのは、以下の4点です。
- 誰に向けて求人を出すのかを明確にし、刺さる表現に落とし込む
- 媒体を“多く出す”のではなく、“合った場所”に出す
- ターゲットごとの関心事に寄り添った魅力づけ
- 現場の空気や働きやすさを“見える化”して、不安を取り除く
採用活動を俯瞰して、「戦略的にかける」と「無駄を抑える」を見極めることが、コスト削減の第一歩になります。
採用コストの抑えどころを見極めることが企業には求められるでしょう。
求人情報の掲載先を見直す際は、「ジョブコンプラスS」をチェックしてみてはいかがでしょうか。
警備業の求人を取り扱っている専門サイトです。
ぜひ資料をダウンロードしてみましょう。