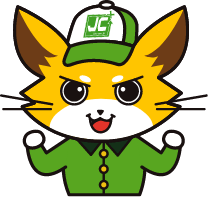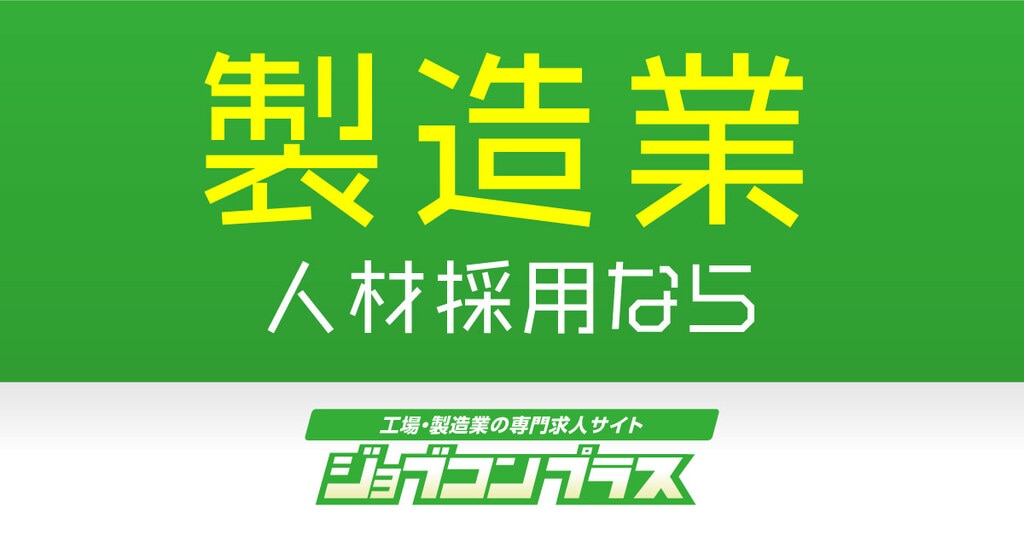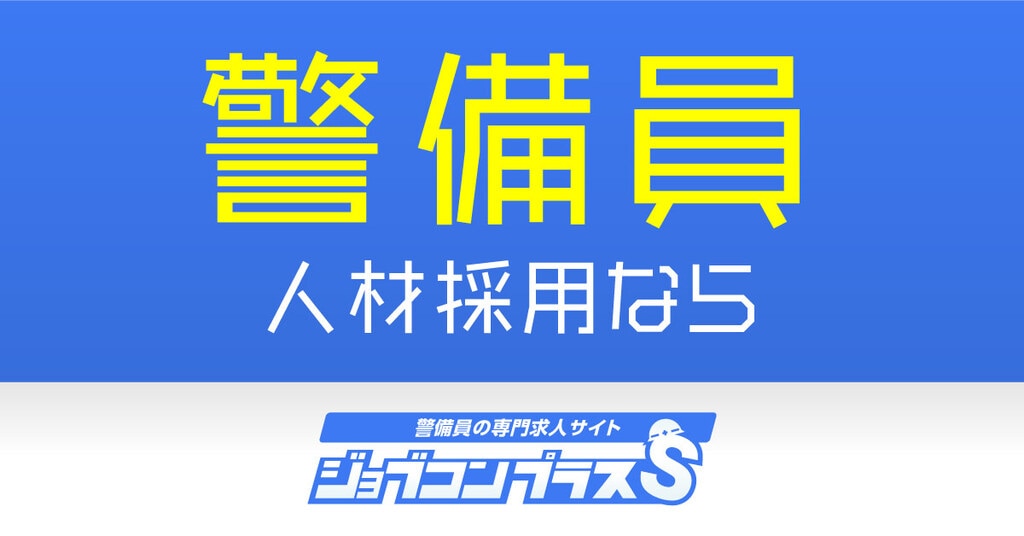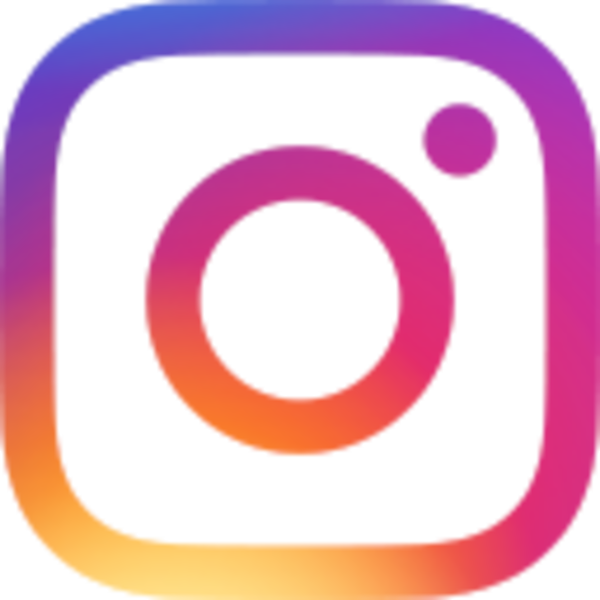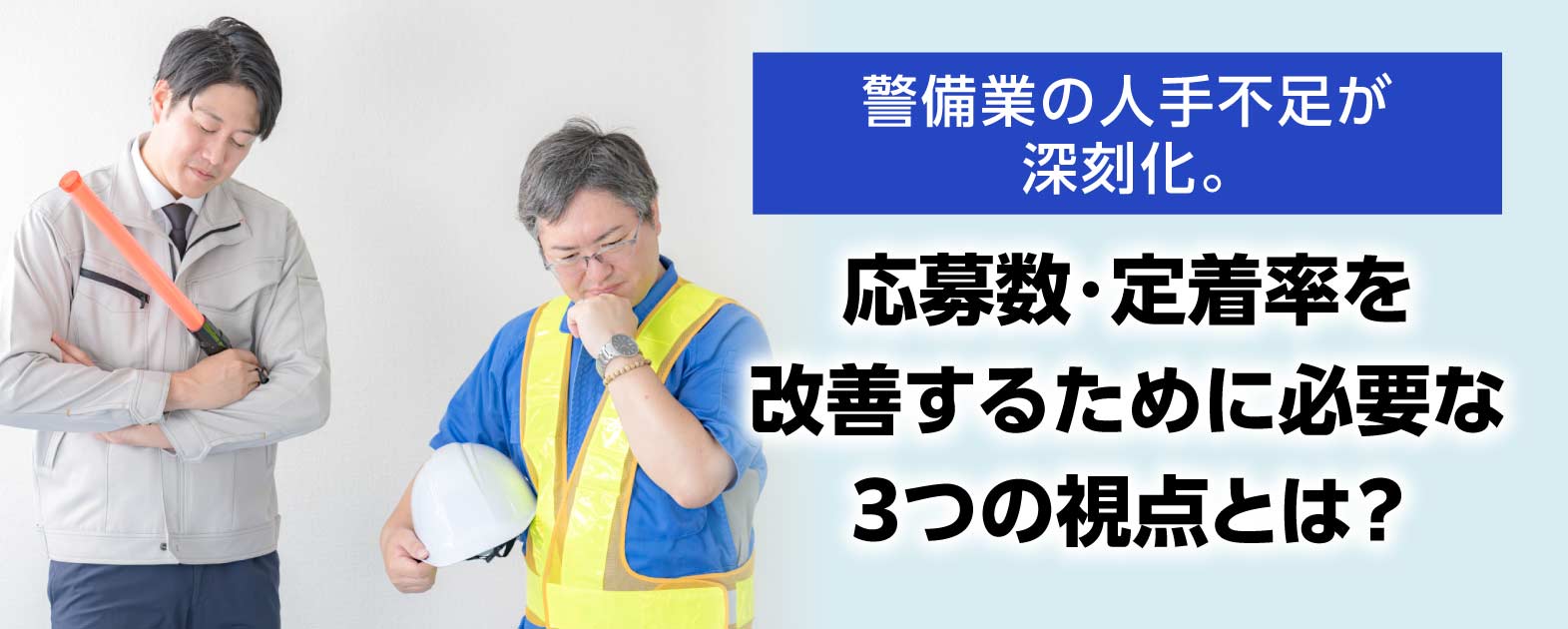
警備業の人手不足が深刻化。応募数・定着率を改善するために必要な3つの視点とは?
オフィスビルやイベントなど常に需要が安定している警備業。
一方で、現場では高齢化や若年層の応募減少、他業界との待遇格差などにより、慢性的な人手不足が深刻化しています。
では、「応募が来ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」という状況を打開するには、どこから見直せば良いのでしょうか?
本記事では、警備業の採用成功に必要な“3つの視点”と“改善の具体策”を事例も交えて解説します。
目次[非表示]
- 1.警備業の人手不足が加速している3つの理由
- 2.警備員の在職年数別(令和6年末)
- 2.1.他業界との待遇競争に勝てない
- 3.採用がうまくいかない企業にありがちな落とし穴
- 3.1.①求人内容が抽象的で刺さらない
- 3.2.②シニア採用一辺倒になっている
- 3.3.③面接・採用後のフォローが不十分
- 4.警備業の採用を成功させる3つのポイント
- 4.1.① 求職者の不安を払拭する情報発信(画像・現場情報)
- 4.1.1.制服姿・現場写真でリアルを伝える
- 4.1.2.「怖そう」「キツそう」のイメージを払拭
- 4.2.若手・女性・シニアのターゲット別訴求
- 4.2.1.若手にはキャリア支援・資格取得を
- 4.2.2.女性には日勤・設備面の配慮を
- 4.2.3.シニアには週2勤務や日勤中心の安心感を
- 4.3.媒体選定と原稿改善で応募の質と量を両立
- 5.成功企業に学ぶ!採用改善のビフォーアフター事例
- 5.1.■ 事例①:県外応募ばかりだった求人が、地場の応募獲得に成功
- 5.2.■ 事例②:「大変さ」も伝える原稿で、応募者の質と定着率を向上
- 5.3.■ 事例③:応募対応の「ムダ」をなくし、取りこぼしゼロへ
- 6.警備専門求人ならではの強みとは?「ジョブコンプラスS」のご紹介
警備業の人手不足が加速している3つの理由
警備業界では「高齢化」「若手の応募減少」「他業界との待遇格差」が重なり、人材不足が年々深刻化しています。ここでは、その具体的な背景を3つの観点から整理します。
高齢化と若年層の応募減少
警備業界では現在、60代・70代のスタッフが多く活躍しており、若手の採用が年々難しくなっています。
実際、警察庁の「警備業の概況(令和6年版)」によれば、60歳以上の警備員は**全体の42.0%を占め、20代の警備員は**全体のわずか5.8%**にとどまっており、30代を含めても1〜2割程度しかいません。
若年層の減少は日本社会全体の課題ですが、警備業界ではさらに深刻です。
主な理由としては、以下のような点が挙げられます:
「体力的にきつそう」「怖そう」などのネガティブなイメージ
キャリアアップや将来性が見えづらい
そもそも若者が警備業を職業選択肢として認識していない
つまり、若者にとって“選ばれにくい業種”になってしまっているのです。
このままでは業界全体の担い手が先細っていく一方。
若年層に響く情報発信や、働きやすい制度づくり、魅力あるキャリアパスの提示が急務です。
離職率の高さ(イメージギャップ・職場環境)
警備業界の離職率は30〜40%と高水準で、採用した人材の定着が難しい状況が続いています。
警察庁『警備業の概況(令和6年版)』によると、警備員の在職年数で最も多いのは「3年〜10年未満」で、187,907人(全体の約32%)を占めています。
一方で「1年未満」が約17.6%、「1〜3年未満」が約20.8%と、短期間で職場を離れる人も少なくありません。
主な理由としては、以下のような点が挙げられます:
仕事内容の実態
求人情報のギャップ
厳しい勤務環境
給与待遇の不満
教育体制やフォロー体制が不十分
これらのように、イメージとのギャップや待遇の不満で高い離職率に繋がっています。
他業界との待遇競争に勝てない
同じく人手不足が叫ばれる他業界に比べ、警備業の給与水準や福利厚生はまだ見劣りするケースが多いです。特に若手や女性にとって魅力的な労働条件の整備が遅れているため、他業界に人材が流れてしまう傾向があります。
採用がうまくいかない企業にありがちな落とし穴
警備業界では深刻な人手不足が続く中、採用に苦戦する企業にはいくつかの共通点があります。ここでは、警備業の採用活動を成功に導くために押さえておきたい注意点を3つの視点から解説します。
①求人内容が抽象的で刺さらない
「未経験歓迎」「シンプルな仕事」といった曖昧な表現だけでは、仕事内容のリアルが伝わらず、結果として応募につながりにくい傾向があります。
特に警備業は職場の雰囲気や業務内容のイメージがつきづらいため、「自分にできる仕事か判断できない」と感じて応募をためらう人も多く見受けられます。
仕事内容・現場環境・フォロー体制を具体的に伝えることが鍵です。
②シニア採用一辺倒になっている
確かに警備業界では60代以上のシニア層が多く活躍していますが、それに頼りきった採用では将来的に人材の偏りや採用難につながる可能性があります。多様な層に向けた打ち出しができていないことが、応募数の伸び悩みや定着率低下の原因となる場合も。
若手・女性・ミドル層へも幅広くアプローチが必要です。
③面接・採用後のフォローが不十分
“応募から面接までのスピードが遅い”“内定後のサポートが乏しい”“入社後の不安が放置されている”こうした対応の遅れや不備が、求職者の離脱や早期退職につながることがあります。
ある調査では「応募から3日以内に面接を設定できた企業の方が、7日以上かかった企業よりも定着率が高い」という結果もあり、採用対応のスピード感が求職者の印象に大きく影響しているといえるでしょう。
「3日以内の面接設定」「内定者フォロー」「入社後の研修」で定着率は大きく改善します。
警備業の採用を成功させる3つのポイント
では、どのようなことを意識したら採用率・定着率ともに改善されるのでしょう。ここでは応募が獲得できるような対策・ポイントを解説します。
① 求職者の不安を払拭する情報発信(画像・現場情報)
制服姿・現場写真でリアルを伝える
求人広告や採用ページに、実際の制服姿や現場で働く社員の写真を掲載することで、業務のイメージが明確になり、不安が軽減されます。とくに「写真付きの求人は、職場の雰囲気や業務内容を視覚的に伝えることができ、画像を掲載していない求人と比べ、応募率が40%増加につながる傾向」という調査もあるほど、視覚情報の効果は大きいと言えるでしょう(※リクルート社調べ)。
「怖そう」「キツそう」のイメージを払拭
警備の仕事は「厳しい上下関係があるのでは」「覚えることが大変そう」など、未経験者にとってマイナスの先入観を持たれることが多いです。現場での穏やかなやり取りや、年齢・性別を問わず活躍する社員の姿を言葉や写真で伝えることで、「ここなら安心して働けそう」という印象に変えることが可能です。
若手・女性・シニアのターゲット別訴求
若手にはキャリア支援・資格取得を
「安定した仕事がしたい」「手に職をつけたい」という若手には、資格取得支援制度やキャリアアップ制度を明示的に打ち出すのが効果的。将来的に管制や教育担当など、多様なキャリアパスがあることを紹介すると、応募へのモチベーションが高まります。
女性には日勤・設備面の配慮を
近年、女性警備員のニーズが高まっており、トイレ環境や休憩スペースといった設備面の配慮、日勤中心のシフトなどを訴求することで安心感を与えられます。「トイレ問題」などは女性応募者の離脱要因にもなり得るため、具体的に改善点や設備写真などを示すと◎。
シニアには週2勤務や日勤中心の安心感を
健康面や体力を考慮したシフト調整のしやすさや、週2〜3日の勤務OK、夜勤なしなどの条件はシニア層からの応募を後押しします。また「60代でも現役で活躍中!」といった先輩事例を紹介するのも効果的です。
媒体選定と原稿改善で応募の質と量を両立
媒体の特性に合わせた「ターゲット設計」がカギ
たとえばミドル層やシニア層を狙うなら新聞折込や地域密着型媒体、若年層にはSNSやIndeedなどのネット媒体が効果的です。それぞれのメディアが得意とするターゲットに合わせ、訴求ポイントや表現方法をカスタマイズすることが成功の第一歩です。
「検索される」キーワードと「読まれる」内容を一致させる
求職者は「日勤のみ 警備」「50代 未経験OK」など具体的なワードで検索します。こうしたニーズにマッチしたキーワードを原稿に含めることで、表示回数・応募数の両方がアップします。
また、入社後のフォロー体制や勤務環境を明確に記載することで、応募後の不安や離脱も減らせます。
成功企業に学ぶ!採用改善のビフォーアフター事例
ここでは、実際に採用課題を抱えていた企業が、求人原稿や掲載戦略を見直すことで成果を上げた改善事例を3つご紹介します。
■ 事例①:県外応募ばかりだった求人が、地場の応募獲得に成功
企業情報:東京都世田谷区/交通誘導警備(アルバイト・パート)
課題:寮希望の県外応募者ばかりで、地元在住の人材を採用できなかった
実施内容:原稿に「地元エリア勤務歓迎」「地域密着」といったエリア訴求を追加
⇒結果:原稿改善からわずか3日で、地元在住の方からの応募を獲得
≪ポイント≫
ユーザーの検索行動データをもとに、より見られている情報に基づいて原稿を修正。勤務地や通勤距離を重視する層に“刺さる”訴求を行うことで、ピンポイントな母集団形成に成功しました。
■ 事例②:「大変さ」も伝える原稿で、応募者の質と定着率を向上
企業情報:愛知県名古屋市/施設警備(契約社員)
課題:他部署からの応募誘導も効果が出ず、応募自体が集まらなかった
実施内容:「駅チカ」「通いやすさ」などのメリットに加え、あえて仕事内容の大変さも記載。リアルな業務内容と、活かせる経験を明確に打ち出した
⇒結果:掲載から1週間以内に、ターゲット層(年齢・地域)に合致した応募を獲得
≪ポイント≫
「良いことだけ書く」のではなく、入社後のギャップを抑えるために“厳しさ”も隠さず記載。誠実な情報開示が志望度の高い応募者の獲得につながりました。
■ 事例③:応募対応の「ムダ」をなくし、取りこぼしゼロへ
企業情報:東京都世田谷区/交通誘導スタッフ(アルバイト・パート)
課題:他媒体との併用による母集団形成は維持しつつ、面接できない時期の応募を減らしたい
実施内容:応募数課金型の媒体にて、自由な掲載スケジュールを組み、対応できない期間は停止運用
⇒結果:長期休暇中の応募停止で、対応可能な時期に集中した応募を受け付けることが可能に。対応漏れやスルー応募がゼロに
≪ポイント≫
応募課金制×掲載期間自由の特性を活かした柔軟なスケジューリングで、応募対応の効率化を実現。担当者からは「他媒体との連携もしやすくなった」と高評価を得ています。
記事でご紹介した内容を、さらに掘り下げて解説した資料を公開中です。
実際の事例や具体的なデータも収録していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください!
資料ダウンロード (応募が来ない…を解決した 求人原稿の工夫とは?)
警備専門求人ならではの強みとは?「ジョブコンプラスS」のご紹介
今回ご紹介したように、採用課題は企業ごとに異なりますが、媒体の特性を理解し、原稿の中身や掲載のタイミングを柔軟に設計することで、大きな改善が可能になります。
求人原稿や媒体の使い方に迷った際は、警備業に強い「ジョブコンプラスS」へのご相談もご検討ください。
ターゲット層に刺さる訴求設計から、無駄のない運用スケジュールの提案まで、実践的な採用支援をご提供します。
以下よりぜひお問い合わせください。
ジョブコンプラスSとは