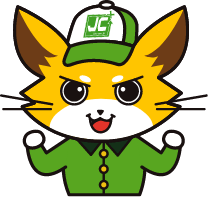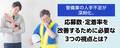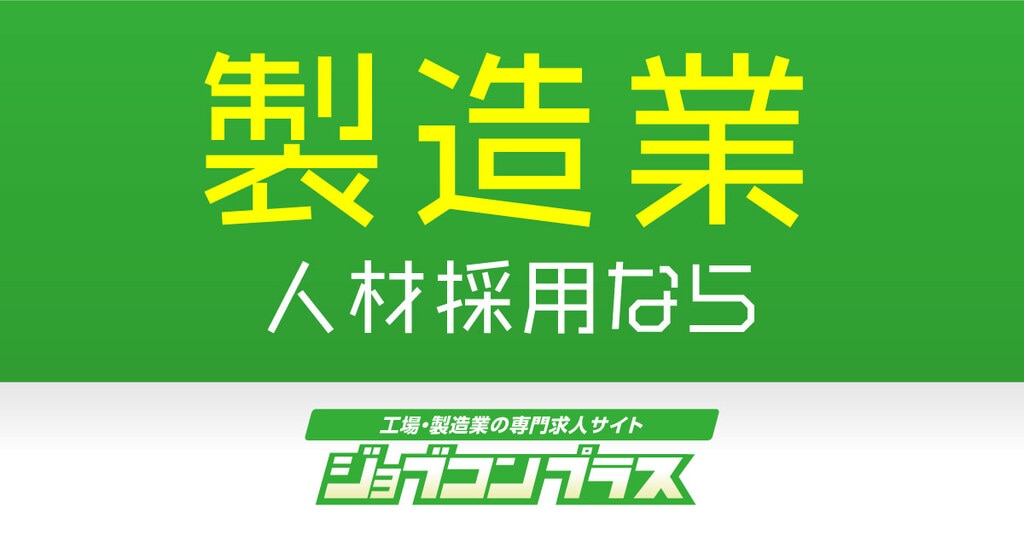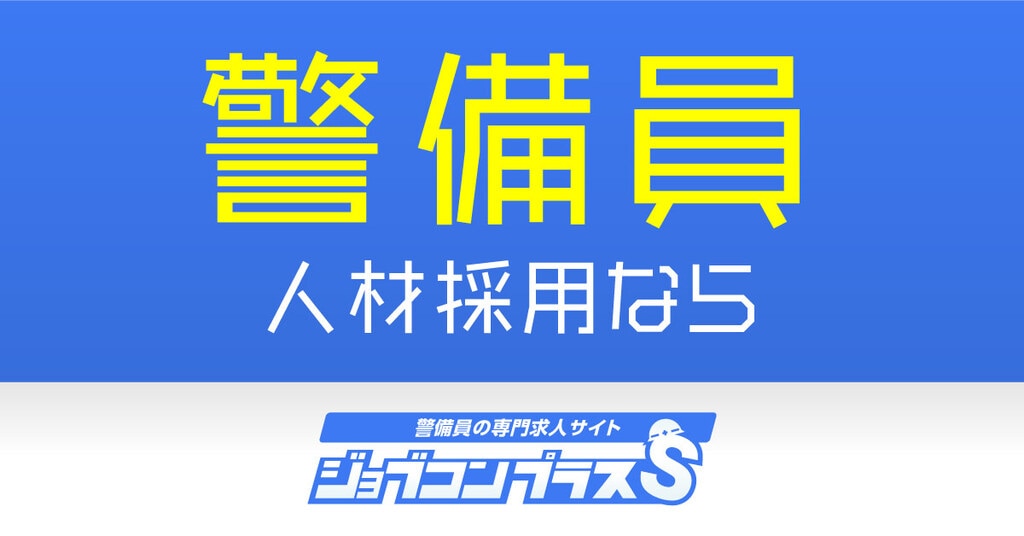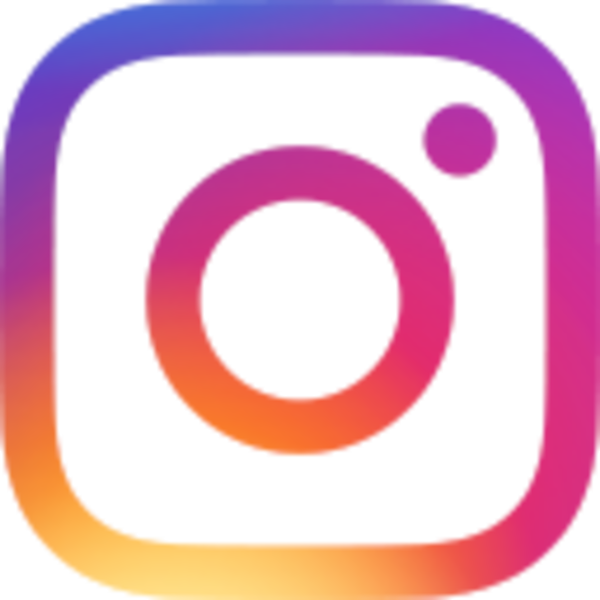製造業の人手不足が止まらない…企業が今とるべき5つの対策とは?
いま、製造業の多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。
「応募がほとんど来ない」「採ってもすぐ辞めてしまう」
とくに中小企業ではこうした声が年々増えており、離職率の高さも悩みの種になっています。
求人広告を出しても反応が薄く、採用単価だけが上がっていく…
そんな悪循環から抜け出すには、人手不足の根本的な原因を理解し、
自社に合った“採用改善策”を見つけることが必要不可欠です。
なぜここまで人材確保が難しくなったのか、企業はこれからどのような対策をとるべきなのか。
本記事では製造業界の人材不足の背景とともに、
その解消に向けた具体的に取り組める対策を5つの視点から解説します。
目次[非表示]
- 1.製造業が人手不足に陥っている3つの背景
- 1.1.少子高齢化による若手不足
- 1.2.離職率が高い労働環境(3Kのイメージ)
- 1.3.働き方の変化とミスマッチの増加
- 2.人手不足による企業への具体的な影響とは?
- 2.1.生産効率の低下・納期遅延
- 2.2.残業過多による既存社員の疲弊
- 2.3.採用単価の高騰・コスト増加
- 3.人手不足を乗り越えるために今できる5つのこと
- 3.1.① ターゲットを明確にし、刺さる求人原稿に見直す
- 3.2.② 働きやすさ(待遇・福利厚生・研修など)の可視化
- 3.3.③ 定着率を高めるオンボーディング整備
- 3.4.④ 多様な人材の採用
- 3.5.⑤ 媒体選定を見直し、業界特化型を活用する
- 4.【事例あり】ジョブコンプラスで採用改善した企業
- 5.まとめ:採用改善に向けてまず取り組むべきこととは?
- 6.製造業採用に特化した求人媒体「ジョブコンプラス」のご紹介
製造業が人手不足に陥っている3つの背景
なぜ製造業でこれほどまでに人材の確保が難しくなっているのでしょうか。
ここではその主な要因を3つに分けて紹介します。
背景を正しく理解することで、今後の採用戦略に活かせるヒントが見えてきます。
少子高齢化による若手不足
日本の少子高齢化が進み、若年層の労働力人口は年々減少しています。
中でも製造業は、若者から「キツイ体力仕事」「経験のいる職種」「働き方が古い」と敬遠されがちで、若年層の就職先として選ばれにくいのが現状です。合わせて入職率も減っています。
新しい人材の確保が困難な一方、定年を迎える人材は急増しており、
需要と供給のバランスは崩れつつあります。
離職率が高い労働環境(3Kのイメージ)
製造業には「キツい・汚い・危険」といった3Kのイメージが根強く残っており、
定着率の低さにもつながっています。
実際には空調完備や働き方の見直しで環境改善が進んでいる企業が多いですが、
働く側にその情報が届いていないケースも。
改善が進んでいても尚就職先として選ばれにくく、
入職してもすぐに離脱してしまうケースも珍しくありません。
労働環境へのネガティブイメージが定着してしまっていることが背景の1つでしょう。
採用活動では、実態とイメージのギャップを埋める情報発信が求められます。
働き方の変化とミスマッチの増加
昨今は「自分らしい働き方」や「ワークライフバランス」を重視して仕事を選ぶ時代へ変わりつつあります。
しかし、製造業の現場は「交替勤務」や「シフト制」、「ルール通りの働き方」など、
柔軟な働き方が難しい環境が多く存在します。
この働き方のギャップが、若年層や主婦層などの価値観のミスマッチへつながっています。
人手不足による企業への具体的な影響とは?
人材が足りないことで生じる影響は、単なる業務の遅延にとどまりません。
生産性の低下、既存社員への過重労働、採用コストの増加といった深刻なリスクが企業全体を圧迫します。ここでは、具体的な影響を3つの観点で解説します。
生産効率の低下・納期遅延
現場の人数が減ることで作業スピードが落ち、生産効率が下がることが懸念されます。
生産効率が低下することにより、製造が間に合わず納期遅れが発生したり、品質低下にもつながり
結果として取引先からの信頼を損ない、継続的な受注にも悪影響を及ぼすことになります。
残業過多による既存社員の疲弊
人員足りない分は既存社員が対応することにより、一人当たりの作業量が増え、長時間労働や
休日出勤が常態化し、社員のモチベーション低下や健康被害に発展するケースもあります。
結果、モチベーションの低下だけでなく、心身の不調や退職にもつながりやすくなり
既存社員の離職、人員確保がさらに難しくなるという悪循環に陥ります。
採用単価の高騰・コスト増加
「とにかく人員をはやく補充したい」と焦って広告費をかけても、
「採用」という結果につながらなければコストばかりかかってしまいます。
また、人材紹介や派遣会社への依存が増すことで、一人当たりの採用単価が跳ね上がり、
企業の利益を圧迫する原因になります。
人手不足を乗り越えるために今できる5つのこと
人材不足を乗り越えるために必要なことは、やはり「人材採用」です。
採用難を解決するには「とりあえず人を集める」のではなく、求職者に響く工夫を取り入れることが大切です。ここでは、製造業の採用担当者がすぐに実践できる5つの改善ポイントを紹介します。
① ターゲットを明確にし、刺さる求人原稿に見直す
まず、採用したい人物像(ペルソナ)を明確にすることで、
ターゲットが興味を持ちそうなキーワードや言葉遣いなどを意識しましょう。
- 若手向け:「未経験歓迎」「月収◯万円以上可」「プライベートも充実」
- シニア層向け:「60代も活躍中」「体力に配慮した職場」
求人はスマホで読まれることが多いため、改行や箇条書きを意識してスマホ表示を意識した文章構成にすることで視認性を高めるのも効果的です。
② 働きやすさ(待遇・福利厚生・研修など)の可視化
自分が実際に働いたら…とイメージできる求人には安心感を持つことができます。
- 実際の写真や動画を使って職場の雰囲気や作業内容を伝える
- 家賃補助や通勤手当、資格取得支援など福利厚生を具体的に記載する
- 入社から仕事を始めるまでの研修の流れや実際の教育係の写真を載せる
このような具体的な情報を記載することで求職者に
「自分に合っている」とイメージさせることで、応募へつながります。
③ 定着率を高めるオンボーディング整備
採用したらそれで終わりではなく、新しく入社した社員がスムーズに会社や業務に馴染めるよう
サポートなどを行うオンボーディングが採用後に最も重要になります。
業務の流れや社内ルール、チーム文化などを理解しやすくすることで、早期戦力化や離職防止に効果があります。
- 入社後の流れ(研修やサポート体制)を可視化
- メンター制度の導入
- 半年後には班長に。資格取得で昇給などキャリアパスの提示
これから先も安心して就業できる・成長できる環境が整っているなど、
将来の見通しを持てる職場は定着率も高くなります。
④ 多様な人材の採用
労働力人口が少なくなっている今、「若い人材」だけに依存するのは危険です。
主婦層やシニア世代・外国人雇用など採用視野を広げることで応募の幅も広がります。
- 主婦(夫)層:日勤のみ・時短・扶養内で働ける柔軟性
- シニア層:経験を活かしながら体力に配慮したポジション提案
- 外国人材:日本語研修や生活支援を充実させ、安心して働ける環境
特に、外国人材の雇用は2015年の約100万人から2023年には205万人と年々増加している。
※厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」より
少ない国内の若手層の採用に絞るのではなく、採用の間口を広くしていくことで
人手不足の解消だけでなく新たな風を入れ込むきっかけになります。
⑤ 媒体選定を見直し、業界特化型を活用する
どの媒体に自社の求人を掲載するのか、求人媒体選びも重要です。
大手総合求人媒体であれば求職者も多いですが、
掲載している企業や記事も多く、採用ターゲットから応募が来るか分かりません。
製造業であれば製造業に特化した媒体に掲載することで、製造に興味のあるユーザーが集まり、応募後のミスマッチも少なく採用率もあがります。
また、掲載するだけでなく、データ分析やレポート機能のある媒体なら、データを見ながらPDCAサイクルをまわし、よりより採用活動を行えます。
媒体は「とりあえず出す」ではなく、「誰に届けたいか」を基準に判断しましょう。
【事例あり】ジョブコンプラスで採用改善した企業
ある企業では、様々な年齢層が働いているから採用の間口が広く
「誰でも働きやすい」というテーマで求人原稿を掲載していましたが、
他社の求人に対して強みを打ち出せずに応募獲得に苦戦していました。
ジョブコンプラスは、応募効果や原稿内容から「逆にどの層にも訴求しきれていない」と
仮説を立て、特定の層に焦点をあてたターゲット原稿を作成するため、職場の雰囲気や待遇・福利厚生など詳しく企業にヒアリングし、原稿のリライトを行いました。
結果、週10件以上の応募があり、一か月で3名を採用することが出来ました。
「誰でも」ではなく「誰に」を明確にし、「あえて訴求するターゲットを絞った」採用で成功につながった好例です。
応募が劇的に増えた事例:https://saiyo.job-con.jp/blog/c147
まとめ:採用改善に向けてまず取り組むべきこととは?
人材不足の現状を打開するには「採用戦略の最適化」が欠かせません。
- 誰に来てほしいのかを定める
- 働きやすさを具体的に伝える
- 定着を支える仕組みを用意する
自社の現状や課題をしっかり見つめ直すことで、新たな魅力を発見するチャンスでもあります。
これらの戦略を一つずつ実践し、人材不足を乗り越える採用活動を行いましょう。
製造業採用に特化した求人媒体「ジョブコンプラス」のご紹介
ジョブコンプラスでは「サービス内容を知りたい」「採用事例が知りたい」といった採用担当者様に対して、無料相談も受け付けています。さらに、ジョブコンプラスのサイトからは資料を無料ダウンロードすることができます。
ジョブコンプラスのサービス詳細・資料はこちら>>
URL:https://saiyo.job-con.jp/contact/factory