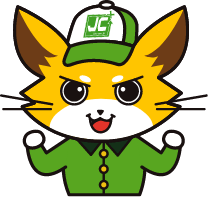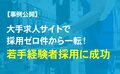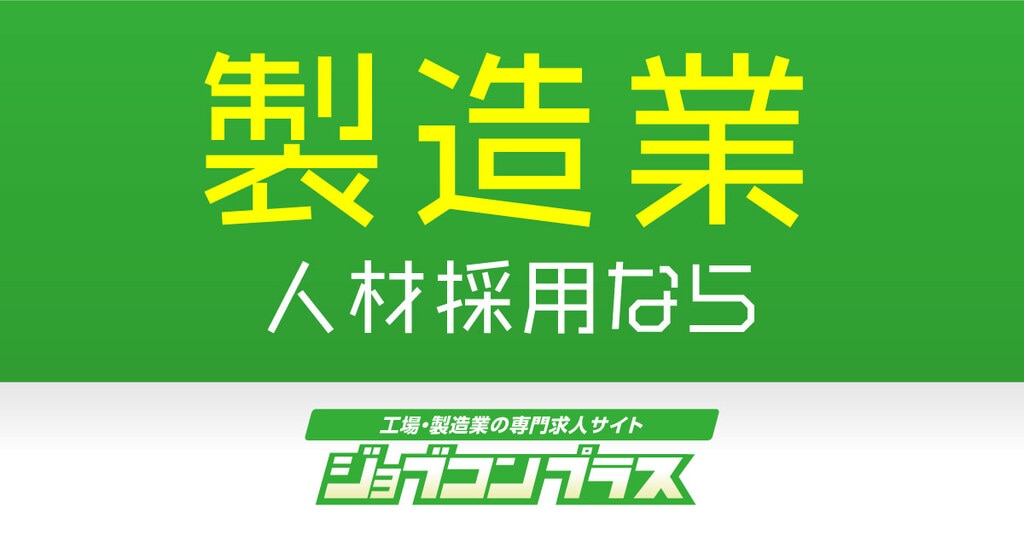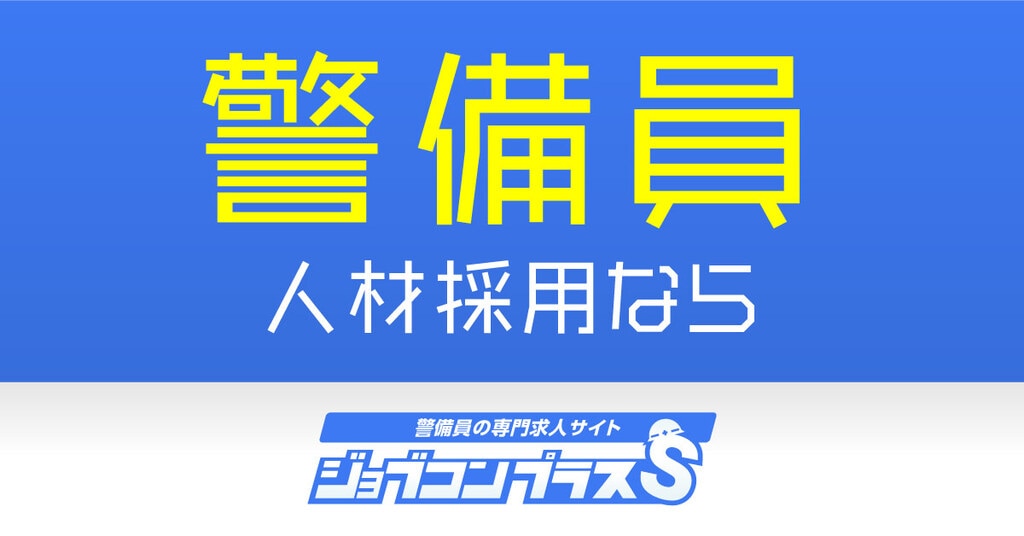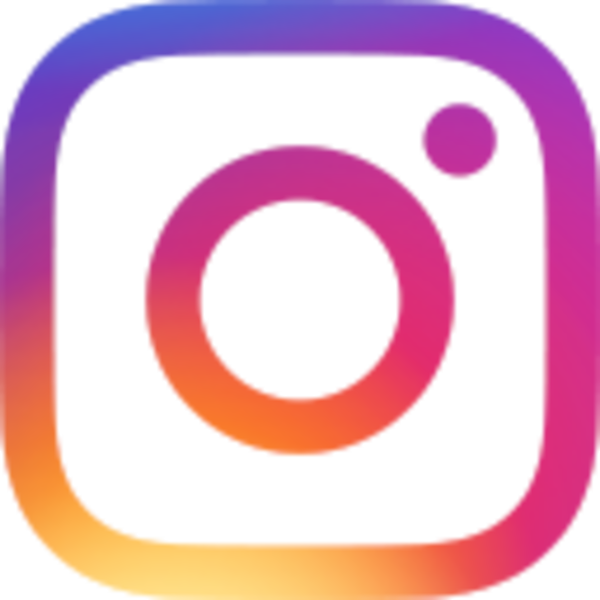燃料の高騰化は運送業の大問題!政府や運送業界の対策を解説
燃料価格の高騰は、運送業界にとって深刻な問題となっています。
オンラインショップの普及や配送サービスの増加により配送量は増えているものの、燃料費の負担で赤字になるという運送会社も出てきているのが現状です。
この記事では、燃料価格が高騰している背景・原因、運送業界への影響、さらに国や運送会社が行うべき対策について紹介していきます。
目次[非表示]
- 1.燃料価格は世界的に高騰している!その理由を2つ紹介
- 1.1.脱炭素化の進展
- 1.2.ウクライナ危機によるロシアへの世界的な経済制裁
- 2.燃料価格の高騰化が運送業に与える影響とは?
- 3.政府が高騰化に対し行った対策
- 3.1.ガイドラインの策定と告知
- 3.2.補助金の支給
- 4.運送業界が高騰化に対し行った対策
- 4.1.業務の効率化を図る
- 4.2.サプライチェーンの最適化
- 4.3.燃料サーチャージ制の導入
- 4.4.運送業界は政府への働きかけと周知活動で対策している
- 5.燃料コスト対策は料金・運賃の設定がポイント!
- 6.まとめ
燃料価格は世界的に高騰している!その理由を2つ紹介
世界的に燃料価格が高騰している理由はいくつかあります。
以下にその理由を解説していきます。
脱炭素化の進展
まずその一つは、世界的に「脱炭素化」の流れが強まっていることです。
温室効果ガスである二酸化炭素の排出量をゼロにする取り組みを日本でも目指しており、日本政府は温室効果ガスの排出を2050年までにゼロとする「カーボンニュートラル」を宣言しています。こうした脱炭素化の動きによって、石油産業への投資は少しずつ縮小しています。
その結果、石油関連の企業の多くが、化石燃料の採掘にかける資金不足に陥っているのです。
ウクライナ危機によるロシアへの世界的な経済制裁
そして二つめに、ウクライナ危機によるロシアへの世界的な経済制裁も燃料高騰化の要因となっています。
ロシアのプーチン大統領は、2022年2月下旬に宣戦布告し、ウクライナへの侵攻を開始しました。
その行動はヨーロッパやアメリカ、日本といった先進国から非難を浴びることになり、同時にロシアへの経済制裁が開始されました。
この結果、ロシア産石油の供給が不安定となり、世界的な燃料価格の高騰を招いています。
こうしたさまざまな要因から原油価格が高騰しており、トラックの燃料である軽油の価格も大幅に高騰しているのです。
燃料価格の高騰化が運送業に与える影響とは?
2020年に入ってからは、新型コロナウイルス感染症によって外出を最小限にとどめる人が増えています。その結果「巣ごもり需要」などで宅配を中心とした運送業の需要は急速に伸びていることは確かです。
国土交通省の発表によれば、2020年度の宅配便の取り扱い件数は実に48億個を超えています。
こうした状況だけを見ると、運送業は景気の良い業界であると感じるかもしれません。
ところが、燃料価格の高騰化によって、かえって運送業は苦しい立場に立たされています。
燃料価格が1円上がっただけで、トラック業界全体でおよそ150億円もの負担が増えるといわれています。つまり、燃料価格が高騰しているせいで需要が伸びても運送業に悪影響をもたらしているということです。
需要の拡大と燃料価格の高騰により、1カ月の燃料費が100万円、200万円と増加する運送業者も少なくありません。この調子で燃料の高騰が続いていけば「走るほど赤字になる」という状況に陥るケースも増加するでしょう。最悪の場合、倒産に追い込まれる可能性も高くなるでしょう。
政府が高騰化に対し行った対策
燃料価格の高騰化に対し、政府が実際に行った対策を紹介していきます。
ガイドラインの策定と告知
国土交通省及び厚生労働省では、運送業者における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を目的に、「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を策定しました。
燃料サーチャージとは、燃料コストの増加分を通常運賃とは別建てとして設定し、荷主に求める仕組みです。
2008年に公表されたこのガイドラインでは、燃料サーチャージの具体的な算出方法や導入手順、事例、相談窓口などが詳しく示されています。
さらに、同省が2020年には「トラック輸送の標準的な運賃」を告示し、軽油価格基準は100円/リットルで算出しています。これを超えた場合、追加の料金を収受できる仕組みを整備しました。
他にも、国土交通省は事業者と荷主が連携し、待ち時間の削減・荷役作業の効率化を図るための事業を平成28年から2年間実施しました。
その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめて発信しています。
補助金の支給
燃料価格の急騰に対応するため、政府は石油元売り会社に対する補助金を支給しています。この補助金額はここ数年間で大きく変動しており、以下のような動きを見せています。
2022年1月:1リットルあたり3.4円
2022年6月:1リットルあたり41.9円に大幅増額
この増額は、石油価格の急騰やそれに伴う経済的な影響を緩和するための措置と考えられます。
その後、2024年には補助金額がピークを迎え、特に7月の支給額は1リットルあたり32.3円と最も高い水準となりました。しかし、2025年1月には1リットルあたり16.5円にまで縮小され、補助金額は徐々に減少傾向を示しています。
補助金の変動は、今後も動向が注目されます。
運送業界が高騰化に対し行った対策

業務の効率化を図る
従来のトラックやハイブリッド車よりも燃料の消費を抑えることができる低燃費車両を導入する事で、燃料の消費を抑えることが可能です。
また、配送コースや納品頻度の見直しなど、配送スケジュールを見直す事で、無駄を省いてより効率的な配送を行うことができます。
サプライチェーンの最適化
製品の原材料の調達から顧客への配送に至るまでの一連の流れを「サプライチェーン」と言います。
現在の流れを見直し改善を行うことで、現場の人数を調整したり、データの分析や在庫管理にAIを取り入れることで効率化が図れます。
燃料サーチャージ制の導入
国土交通省が制定した「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を基に、荷主や元請との交渉を行い、コストの増減分を別建ての運賃として設定を行います。
ただ、今の厳しい状況からすぐに交渉を行い設定することは難しいため、普段から燃料コスト削減に努めていることや荷主企業とコミュニケーションを取るなど、信頼関係を築いておくことで、交渉もスムーズに進めることが出来ます。
運送業界は政府への働きかけと周知活動で対策している
もちろん、運送業界も高騰する燃料価格の影響を軽減すべき取り組みを積極的に行っています。
運送会社の中でも、中小規模の場合は荷主企業との力関係から燃料が高騰した分の価格交渉は難しいのが現状です。そのため、零細企業ほど高騰化の影響を大きく受けてしまうことが懸念されます。
そのような状況の改善を目指して全日本トラック協会が行ったのは、国土交通大臣や内閣官房長官に向けての「荷主企業へ働きかけを求める要望書」の提出です。
こうした動きをもとに、国土交通省は「燃料サーチャージ」や「標準的な運賃」を改めて荷主企業や団体に周知しています。
そして、「運賃・料金の不当な据え置きは法律違反のおそれがあり、要請、勧告・公表の対象となる」ことも発表しました。つまり、運送業界が自ら取った動きが形となり、燃料価格の高騰化から救済する措置が取られたことになります。
国道交通省の告示を受け、全日本トラック協会も荷主企業へパンフレット送付をしたりインターネット広告を利用したりするなど周知活動に力を入れています。
燃料コスト対策は料金・運賃の設定がポイント!
燃料価格の高騰化は、運送業界に大きな影響を及ぼしています。
しかし、運送業界が自ら行動を起こすことで国が救済措置を取る形になり、燃料サーチャージなどが改めて告示されました。
実際の燃料高騰分の負担を運送業者が具体的な数字で明確にすることで、荷主企業が燃料サーチャージに同意するケースは増えてきています。
今後も国と運送業者が連携を取ることで、適正な価格交渉が行えるような業界作りが求められます。
まとめ
燃料価格の高騰は、脱炭素化による石油産業への投資縮小や、ウクライナ危機によるロシアへの経済制裁など、さまざまな要因が絡み合って発生しています。これにより、ロシアからの石油供給が不安定になり、燃料価格は世界的に上昇を続けています。
一方で、新型コロナウイルス感染症による「巣ごもり需要」の増加や、オンラインショッピングの普及により、宅配を中心とした運送業の需要は急速に拡大しました。しかし、燃料費の高騰により、運送業者は「走るほど赤字になる」という深刻な状況に直面し、倒産のリスクも高まっています。
こうした課題を乗り越えるためには、政府のガイドライン活用や補助金の受給に加え、業務効率化や自社内での改善施策を進めることが重要です。さらに、燃料高騰時に運送業者が負担しているコストを具体的な数値で示すことで、荷主企業の理解を得ることができます。その結果、燃料サーチャージ制への同意を得て適正な価格交渉を進める道が開けるでしょう。
燃料価格高騰の影響を最小限に抑え、持続可能な運送業界を実現するためには、政府、運送業者、荷主が協力して取り組むことが求められます。