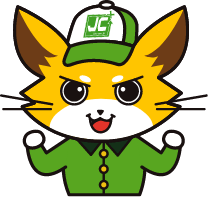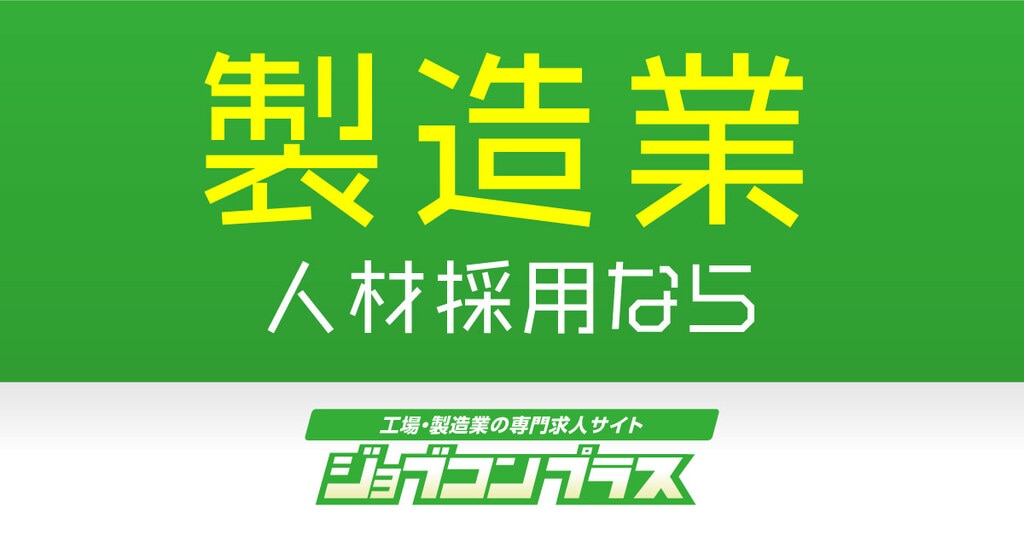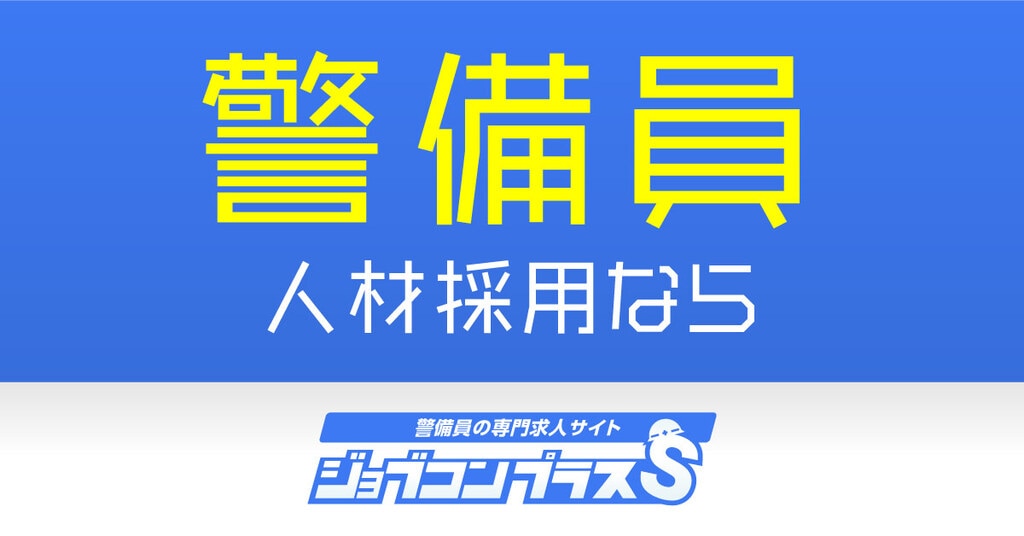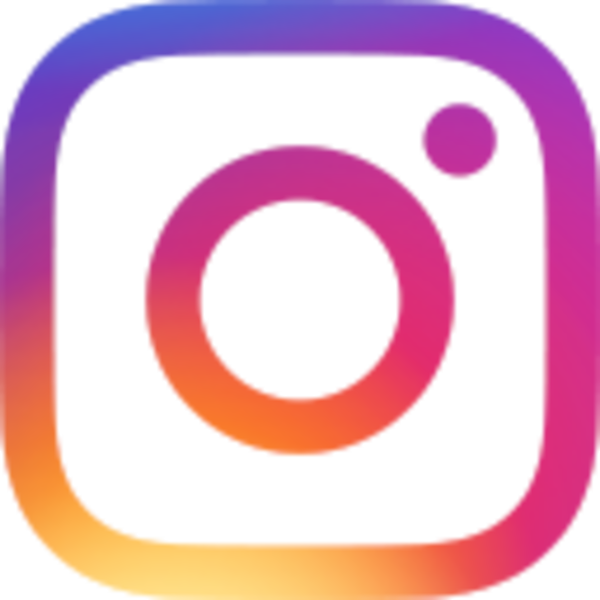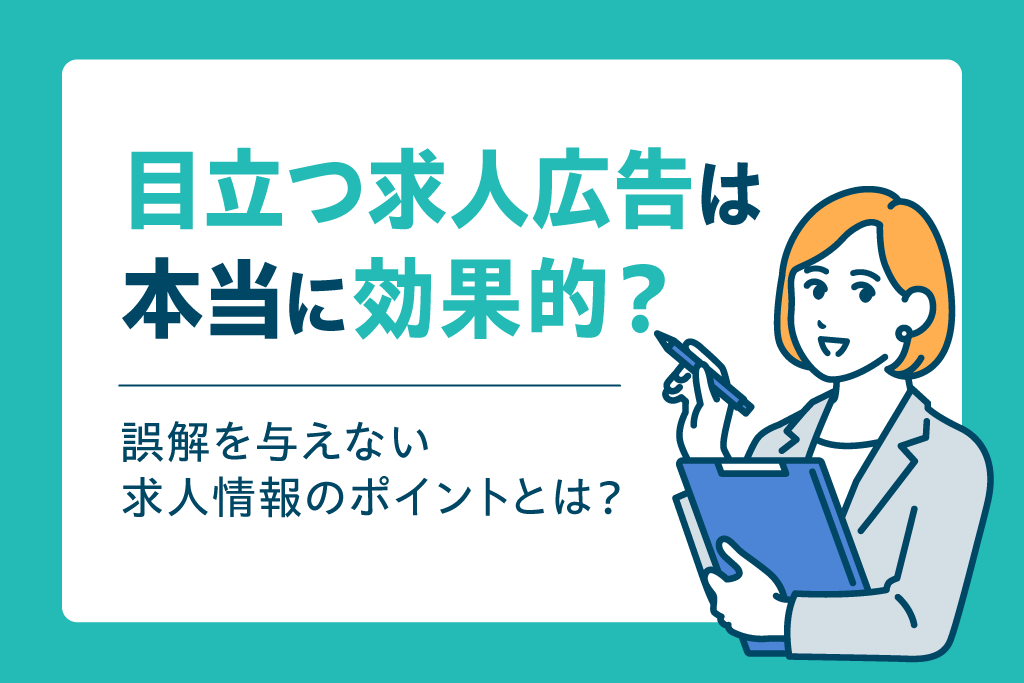
【募集・採用の基礎知識④】目立つ求人広告は本当に効果的?一歩間違えたら虚偽広告!?誤解を与えない求人情報のポイントを解説します!
出典:公益社団法人全国求人情報協会「募集・採用の基礎知識」
「応募を増やすためにインパクトが大事です!」という言葉をよく聞きますが、採用成功の為には「沢山の応募者を集めること」や「インパクトのある広告を打つ」「良いことばかり書く」という、いわゆる『目を惹く求人』を作ることが良い事とは限りません。
表現を大げさにしてしまった結果、求職者に誤って伝わることも…。
では何を重視して記載していくべきなのかを解説していきます!
目次[非表示]
- 1.求人広告のインパクトよりも重視すべきポイント
- 1.1.「目を惹く見出し」以外にも信頼を損ねないための情報をプラスする
- 1.1.1.過度な誇張表現が信頼を損ねる可能性がある
- 1.2.虚偽や誇張を避け、実態に即した情報を提供する重要性
- 1.3.求職者が求人内容に求めている情報を具体的に記載
- 1.3.1.仕事内容の具体性
- 1.3.2.入社後の研修や教育体制
- 1.3.3.賃金の詳細
- 1.3.4.職場の雰囲気・人間関係
- 1.4.誤解を招く表現に注意
- 1.4.1.誤解を招く表現①未経験大歓迎!入社後の研修もバッチリ!
- 1.4.2.誤解を招く表現②すぐに働けます!
- 1.4.3.誤解を招く表現③時間・曜日相談に応じます
- 2.求人広告に虚偽の内容を記載することで雇用主側が被るデメリット
- 2.1.応募者のミスマッチによる早期離職
- 2.2.労働トラブルの発生
- 2.3.信頼性の低下
- 2.4.長期的な採用活動の困難化
- 2.5.場合によっては違法の可能性も
- 3.親会社・グループ名での求人募集は問題ない?
- 3.1.親会社が子会社の雇用を行う場合
- 3.2.出向予定者の募集
- 4.まとめ:正確な情報で信頼される採用活動を
求人広告のインパクトよりも重視すべきポイント
求人広告は、目を引く表現だけでなく、求職者が本当に知りたい情報を的確に伝えることが重要です。インパクトを優先しすぎて内容が実態と異なっていたり、不明確な記載があると、応募者の信頼を損ねるだけでなく、採用後のミスマッチやトラブルを招く原因にもなります。
ここでは、求職者にとって魅力的で信頼される求人広告を作成するために、押さえておきたいポイントを解説します。

「目を惹く見出し」以外にも信頼を損ねないための情報をプラスする
過度な誇張表現が信頼を損ねる可能性がある
求人広告の「100名大募集!」や「大量募集!」といった表現は、求職者の目を惹くことはできますが、同じ内容の広告が何回も続くと次第にその広告が不自然に感じられ、疑念を抱くようになります。
求職者は、「本当に大量の人員が必要なのか」「過去にどれくらいの人数が採用されたのか」に関心を持つことが多く、虚偽や誇張があると不安を感じて応募を避けることになります。
虚偽や誇張を避け、実態に即した情報を提供する重要性
実際とは違う虚偽の内容や誇張した表現は避け、労働条件だけでなく詳細な仕事内容や教育研修内容、職場情報といった内容をプラスで記載する必要があります。それらを具体的に明記したり、透明性のある情報提供をすることで、求職者が仕事に対する理解を深め、応募意欲を高めることができます。さらには求職者の信頼を獲得し、結果的に質の高い応募者を引き寄せることに繋がります。
求職者が求人内容に求めている情報を具体的に記載
求人情報において、求職者が特に重視するのは以下の項目です。
- 仕事内容の具体性
- 入社後の研修や教育体制
- 賃金の詳細
- 職場の雰囲気・人間関係
それぞれ詳しく見ていきましょう。
仕事内容の具体性
求人情報を読む際に真っ先に気になるのは「自分にできる仕事かどうか」です。仕事内容が漠然としていると応募をためらってしまうこともあります。実際に作業している姿を具体的にイメージできる情報が求められます。
作業の詳細な手順だけでなく、チームで行うのか個人で行うのかといった作業体制や、一日の流れも含めて説明することが効果的です。
特に製造業の場合は、取り扱う製品の重さや大きさ、物流業の場合は配送範囲など、物理的な要素も具体的に記載すると良いです。
また、経験が必要ない場合は専門用語を使わずに、誰にでも分かりやすい言葉に置き換えることで、未経験の方にも伝わりやすくなります。
入社後の研修や教育体制
入社後にどのようなサポートが受けられるのかを重視する方もいます。特に未経験者や新しい業界に挑戦する人にとって、研修や教育体制がしっかりしていることは安心材料となります。
例えば、初日のオリエンテーションや基本的な業務の説明に加え、マニュアルの有無、習熟度に応じたサポート内容などを詳しく記載しましょう。
賃金の詳細
給与は日々の生活を支える重要な要素です。その中でも特に「手当の内訳」は、応募を検討するうえで大きな判断材料となります。曖昧な表現ではなく、具体的な金額や条件を明記することで、求職者に安心感を与えることができます。
例えば、月給26万円に20時間の残業手当がつく場合「月給26万円+諸手当」よりも、「月給26万円+残業手当(32,500円/20時間分)」の方が、残業手当が時間に応じて増減する可能性があることが伝わりやすくなり、透明性が高まるため、求職者からの信頼感向上にもつながります。
皆勤手当や住宅手当など、支給条件や金額の上限を明示することも誤解を防ぐ重要なポイントです。
なお、最低賃金を下回る求人は掲載が禁止されているため、厚生労働省の特設サイトでしっかり確認しましょう。給与を正しく記載していないと、求職者とのトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
職場の雰囲気・人間関係
転職先の職場の雰囲気や人間関係に不安を抱く方は少なくありません。これらをしっかり記載することで、採用後のミスマッチ防止や、早期離職のリスクを軽減する効果も期待できます。
例えば、「風通しの良い職場」「アットホーム」といった抽象的な表現よりも、具体的な取り組みやエピソードを盛り込んだり、社員インタビューや職場写真を活用することで、求職者自身がそこで働くイメージができ応募に繋がりやすくなります。さらに、男女比・定着率・有給取得率などの実際の数値データを記載することも効果的です。
求職者が仕事を探す際、重要視している項目は「賃金に含まれている手当の内訳」「職場の雰囲気・人間関係」が上位にあげられています。
また、パートアルバイトでは「勤務体系の柔軟性」を重視するとの声が多いようです。求職者が知りたい情報を積極的に記載し、ターゲット層にアピールすることが採用成功につながります。
誤解を招く表現に注意
以下のような表現は、応募者に誤解を与える可能性があるため、慎重に使用しましょう。
「未経験者歓迎!」と記載しながら、実際には高い専門性が必要な場合
「すぐに働けます!」という曖昧な表現
「時間・曜日相談可」と記載しながら、実際は柔軟性が低い場合
求職者の期待値と実際の条件にギャップがあると、不信感を招き、応募や採用後のトラブルにつながる恐れがあります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
誤解を招く表現①未経験大歓迎!入社後の研修もバッチリ!
「とってもカンタン作業♪」「未経験者大歓迎!」と書かれた仕事だったのに、実際は未経験ではできないような難しい仕事だった。「丁寧に教えます」と書いてあったのに、いざ入社してみたらほったらかしだった。など、応募者は労働条件以外の点にも注目して応募します。
仕事の難しさや教育については、受け取る側の主観や考え方によって違いが生じる為、誤解を招いてしまわないような対応や表記を心掛けましょう。
誤解を招く表現②すぐに働けます!
「すぐ」という表現は期間が曖昧であるため、求職者が翌日には働けると思っていたのに1週間後の勤務開始と案内された…など期待値のずれが生じる可能性があります。
このようなギャップは、求職者の不信感を招き、応募を躊躇させたり、採用後のトラブルにつながる可能性があります。具体的な勤務開始時期を明記し、求職者の誤解を防ぐよう心掛けましょう。
誤解を招く表現③時間・曜日相談に応じます
「相談に応じます」という表現では、どの程度の柔軟性があるのかが曖昧です。例えば、時短勤務が可能なのか、特定の曜日だけの勤務が認められるのかといった詳細をできるだけ記載することがおすすめです。
「すぐに働けます!」「時間・曜日相談に応じます」と表記されている場合、応募者は「自分自身の希望を聞いて貰える」と判断します。
本当に相談に応じて対応することが可能であればよいですが、「すぐに働ける仕事は埋まってしまった」「実は土日は出勤してほしい」となると虚偽広告やおとり広告と誤解されてしまいます。
求人広告に虚偽の内容を記載することで雇用主側が被るデメリット

求人メディアは、法により許可や届け出などが義務付けされている事業ではありません。しかし、全国求人情報協会の会員をはじめ、求人メディアが取り扱う求人広告は、各々が自主的な規制により定めた基準に沿って確認を行い、一定のルールのもと掲載しています。これは読者・ユーザーから信頼を得るほど求人広告の応募反響を高められるという考えがあります。
応募者のミスマッチによる早期離職
求人広告に誤解を招く情報が記載されていると、入社した従業員が仕事内容や条件に不満を持ち、早期離職する可能性が高くなります。これにより、企業は再度求人を出す手間とコストを負担することになります。
労働トラブルの発生
労働条件が実際と異なる場合、入社後に従業員が不満を抱くことになり、トラブルが発生する可能性が高くなります。労働環境に不満を持った従業員が早期に退職したり、労働争議に発展したりするリスクが増えます。
信頼性の低下
求人広告に虚偽の情報が含まれていると、応募者からの信頼を失うことになります。一度信頼を失うと、今後の求人活動や企業イメージに大きな影響を与え、応募者の数が減少する恐れがあります。
長期的な採用活動の困難化
企業が過去に虚偽の求人広告を出していた場合、今後の採用活動で応募者が企業を避けるようになることがあります。透明性と誠実性を欠いた企業には、優れた人材が集まりにくくなります。
場合によっては違法の可能性も
求人広告に記載されていた条件と実際の労働条件が相違していても、すぐに違法となるわけではありませんが、求人広告の内容に対して条件変更ありきで募集していた場合は、労働基準法や職業安定法に違反する可能性があり、法的責任を問われることがあります。
「広告に書いていなくても面接で説明すれば大丈夫だろう」という考えはトラブルの元です。
「そんなことは広告に書いていなかった」「広告に書いてあれば応募しなかった」と応募者は思ってしまいます。
例えば、試用期間中は労働条件が異なる、残業が恒常的にある、交通費支給に規定があるなどの場合は、実態に沿った表示をするようにしましょう。
応募数が予想外に多い為書類選考を実施するなど、応募方法を変更した場合「広告に記載がなかった」という不満も多く、変更理由を説明するという対応が必要になります。
親会社・グループ名での求人募集は問題ない?

大手グループ会社の子会社が採用活動を行う際、子会社名で募集しても応募がなかなか集まらないことがあります。
「知名度のある親会社名かグループ名で求人広告を出したい」あるいは「親会社で採用して子会社に出向という形で人を回してもらいたい」と思うこともあるでしょう。
そのような募集をする際は、職業安定法の改正により「労働者を雇用しようとする者の氏名・名称を明示する」ことが決まりました。子会社で雇用するのであれば、子会社の名前を明示する必要があります。
親会社が子会社の雇用を行う場合
第三者(親会社)が求人者(子会社)に代わって労働者の募集を行うと、委託募集という形となり、職業安定法第36条により原則として許可が必要となります。
また、親会社の名前を出したい場合でも「○△会社の関連会社です」という程度の表現にとどめましょう。
グループ名で募集する場合、各社がそれぞれの募集内容を明示し、採用の予定がないのに募集会社として表示したり、採用されれば親会社に勤務できるかのような表現は避けてください。
出向予定者の募集
出向には2種類あります。
- 在籍型出向:採用された会社に籍を置いたまま出向する形態
- 移籍型出向:採用された会社と労働関係を解消し、出向先の労働者となる転籍を伴う形態
労働契約法第14条では、「出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定などの事情に照らして、権利を濫用したものと認められる場合じゃ無効とする」と定めています。
つまり、出向命令は会社から一方的に出せるものではなく、「当該労働者の同意その他これを法律上正当付ける特段の証拠(労働契約上の根拠)」が必要とされます。また、出向によって労働条件が著しく低下することがないようにしなければなりません。
まとめ:正確な情報で信頼される採用活動を
インパクトのタイトル、見出し、画像や、大手グループの名前を使って求人募集をすれば応募者を集めることはできるかもしれません。しかし、その表現に偽りや実際の状況と差異がないか一度確認をし、求職者とのイメージの違いを出来るだけ無くさなければ、マッチング率の高い採用は難しいでしょう。
より良い質の求職者と出会うために、掲載原稿の工夫だけではなく、正確な情報を伝えられるように重視すべき点を見直し、法律や媒体上のルールに則った求人内容を記載するようにしましょう。