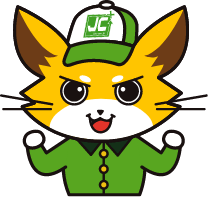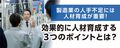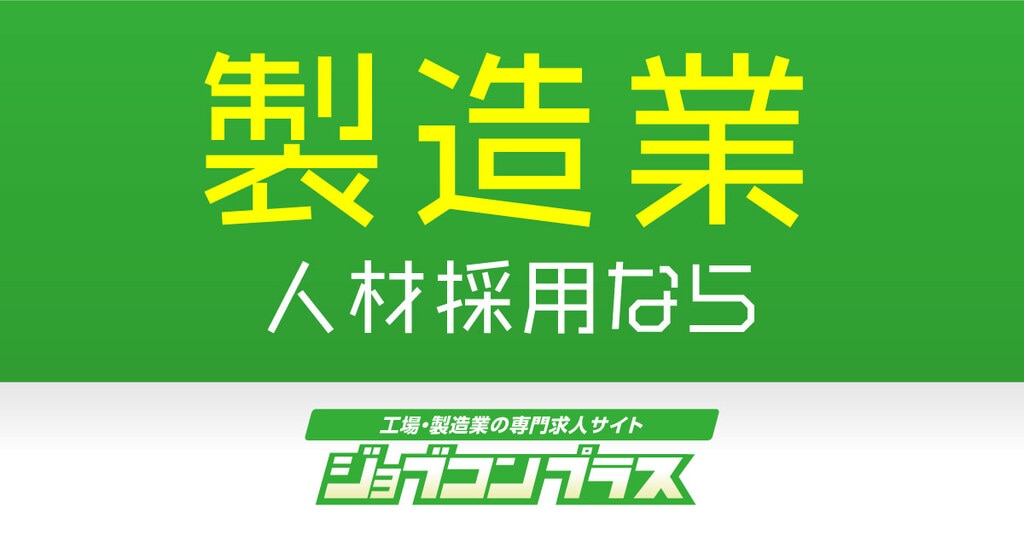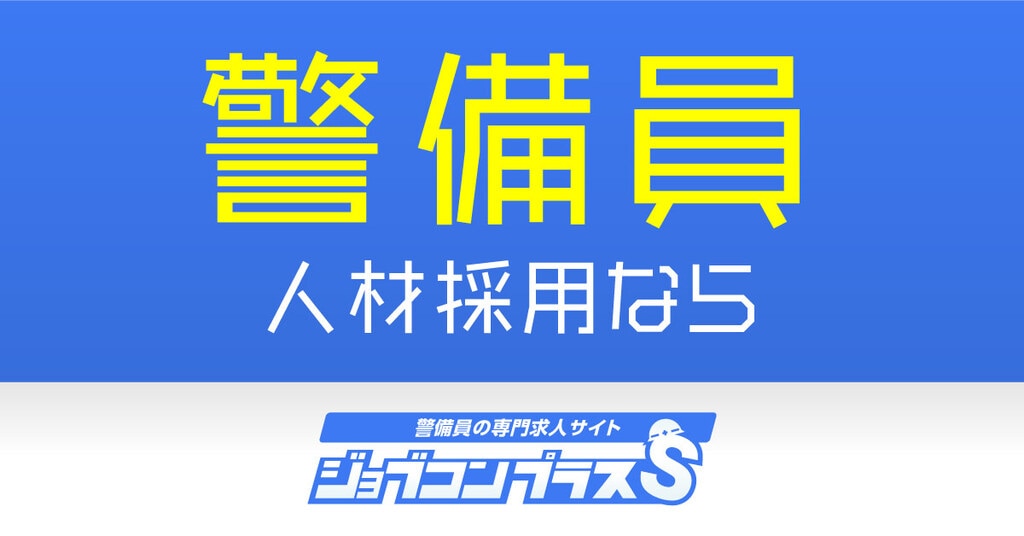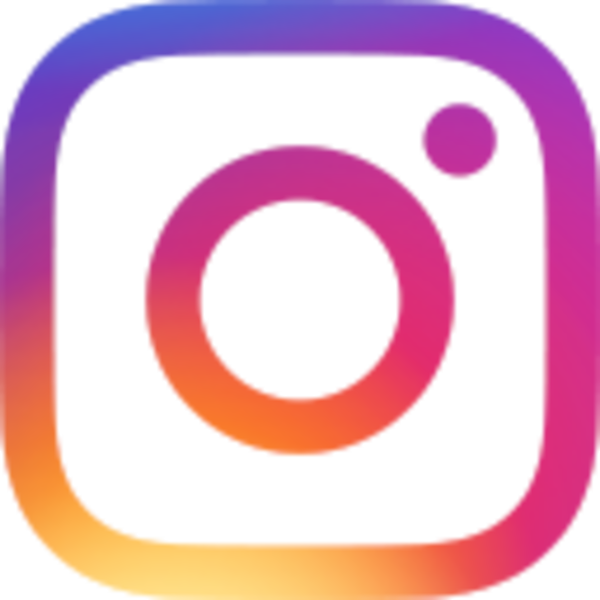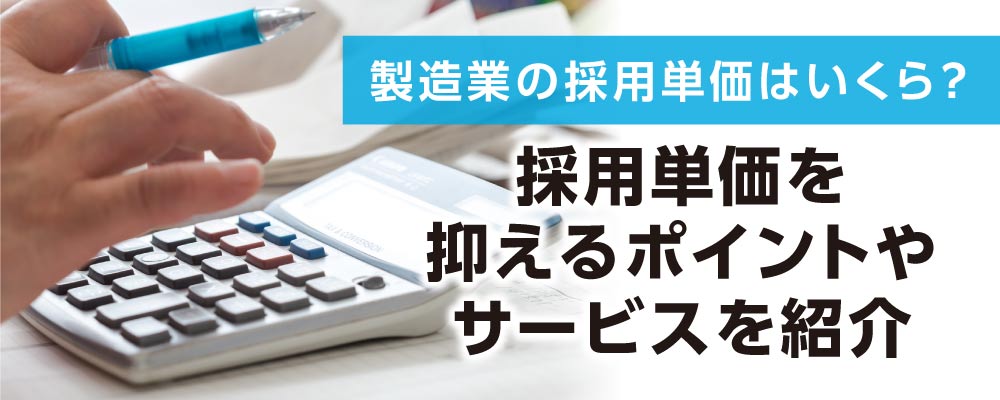
【製造業の採用単価は平均102万円】高騰の原因とコストを抑える3つの対策とは?
製造業の採用単価は、他業界に比べて1人あたり約100万円と高くなりがちです。
人手不足が続く中、会社の中で採用にかけられる予算上限も決まっているため「採用したいのに予算が足りない」「求人を出しても応募が来ない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
費用を少しでも抑えて一緒に働いてくれる方を見つけたいところですよね!
そこで、本記事では採用単価が高くなる原因から、無駄なコストを削減しながら成果を出す3つの具体施策、そして製造業専門の求人サービスまでをわかりやすく解説します。
コストパフォーマンスを少しでも改善できる採用手法を選んでいきましょう!
目次[非表示]
製造業の採用単価はいくら?
製造業は採用コストが高いと言われていますが、他の業界と比べてどのぐらい高いのでしょうか。次から、中途採用の1人当たりの業界別平均採用コストを紹介しましょう。
業種別 |
新卒採用 |
中途採用 |
建設業 |
69.4万円 |
97.8万円 |
製造業 |
69.7万円 |
102.3万円 |
流通業 |
67.7万円 |
55.5万円 |
金融業 |
84.8万円 |
58.2万円 |
サービス・情報業 |
78.1万円 |
86.8万円 |
(出典:株式会社マイナビ様「中途採用状況調査」2019年)
この調査を見てわかる通り、製造業の中途採用における1人あたりの平均採用単価は約102.3万円(※マイナビ「中途採用状況調査」より)と、全業種の中でも高水準です。
流通・飲食などの業界と比べて3〜4倍になるケースもあり、限られた予算での採用活動が大きな課題となっています。
実は、これには大きな理由があります。
それは、製造業の場合、一度に多くの人材を採用するわけではないからです。
たとえば、流通業(特に小売・飲食・サービスなど)では、ホールスタッフや販売員など一度の求人で複数名の募集をかけます。しかし、製造業の場合は少人数の採用が中心となります。
そのため、どうしても1人あたりの採用単価が高くなってしまうのです。
採用単価の計算方法
採用コストとは、会社が人材を採用するまでにかかるコストのことです。コストの中には、求人情報を掲載したり、応募者の面接をしたりする際にかかる費用などが含まれます。
採用単価は「採用コスト÷採用人数=採用単価」の数式に当てはめれば算出できます。
たとえば、採用のための活動に300万円の費用がかかったとしましょう。その結果、3人採用できた場合、採用単価は100万円になります。
この数式に記載されている「採用コスト」には2種類あります。「外部に支払うコスト=外部コスト」と「社内で発生するコスト=内部コスト」です。
2種類の採用コストを抑えることができれば、採用単価も低くなります。特に外部コストはどの企業にも共通するため、改善しやすいポイントが多くあります。
それぞれのコストの中身について、次で詳しく見ていきましょう。
採用コストの内訳
採用活動にかかるコストは、大きく「内部コスト」と「外部コスト」に分けられます。どちらも見落としがちな部分に無駄が潜んでおり、採用単価を正確に把握するためには両方の視点が必要です。
内部コストの具体例
内部コストとは、自社内で発生する人件費や作業工数によるコストです。たとえば、以下のような費用が該当します。
- 採用担当者の人件費(工数×時給換算)
- 面接対応にかかる現場社員の稼働コスト
- 募集~内定までの進捗管理に使う工数
- 社内説明会やオリエンテーションの準備・実施費用
たとえば、面接1回につき担当者2名・1時間の稼働があるとすれば、1名の採用で10万円以上の人件費が発生するケースもあります。
このような「見えにくいコスト」も含めて採用単価を把握することが重要です。
これらは外部に支出しているわけではないため見過ごされがちですが、実際には採用活動に大きな労力と時間がかかっており、結果的に採用単価に影響を及ぼしています。
外部コストの具体例
外部コストは、採用にあたって外部業者や媒体に支払う直接的な費用です。代表的な項目は以下の通りです。
- 求人広告の掲載費(媒体・期間・掲載プランによって変動)
- 人材紹介会社への成果報酬
- 合同説明会・就職イベントへの出展費
- 応募者との連絡に使うシステムやツールの利用料
外部コストは比較的見える化しやすいため、削減対象として着手しやすい反面、費用を下げすぎると質の高い母集団が集まらず、逆に採用単価が高くなるリスクもあります。
コストと成果のバランスを見極めることが重要です。
採用単価が高くなる4つの原因
採用単価が高止まりしてしまう背景には、いくつかの共通した課題があります。特に製造業においては、下記の4つが主な原因とされています。
ミスマッチによる早期離職
採用後すぐの退職は、企業にとって最も無駄なコストになります。とくに製造業では、仕事内容や就業環境への理解不足からミスマッチが起きやすく、早期離職に繋がる傾向があります。
ミスマッチによる早期離職は、1名あたり100万円超の採用コストが数週間で無駄になる事態を引き起こします。
特に現場実習や研修にコストがかかる製造業では、損失が大きくなりがちです。
事前に業務内容や職場の雰囲気を正確に伝えること、面接時に動機や適性を丁寧に見極めることで、離職リスクを抑えることができます。
採用媒体の選定ミス(費用対効果の悪化)
求人媒体にはそれぞれ得意な業種・職種があり、製造業との親和性やユーザー層は大きく異なります。
自社の求める人材像と合わない媒体を使い続けると、多額の出稿費をかけても応募が来ない、費用ばかりがかさむといった事態を招きます。
たとえば、「営業職に強い媒体」で製造職の求人を掲載しても、求職者に見られることすらなく、出稿コストがそのまま無駄になってしまいます。
その結果、採用単価が跳ね上がり、費用対効果は著しく悪化します。
製造業に強い媒体を選定することで、ターゲット人材に効率よくリーチでき、費用対効果の高い採用が可能になります。
応募数はあるのに歩留まりが悪いケース
応募が一定数あっても、「面接に進む人が少ない」「内定辞退が多い」といった歩留まりの悪い状態が続くと、1人あたりの採用コストは一気に上昇します。
原因は求人原稿の情報不足(求人内容とのギャップ)や応募後の対応スピード、選考の一貫性の欠如・煩雑さなどが挙げられます。応募から面接までのスピード感を高める、現場との連携を強化するなど、プロセス改善がカギになります。
特に製造業では応募から面接までに数日でも空くと他社に流れるため、即日連絡やシンプルな選考フローの整備が重要です。
オンライン対応の遅れ、選考プロセスの長期化
コロナ禍以降、オンライン面接や動画説明会は一般化していますが、未対応または対応が遅い企業では応募者離脱が発生しやすくなります。
たとえば、「書類選考に1週間」「面接は来社のみ」といった旧来型の選考では、選考途中での辞退が相次ぎ、採用に至らないままコストだけがかかってしまうケースも少なくありません。
特に20〜30代の求職者は、複数企業に同時応募しているのが一般的です。スピード感のない対応は、それだけで他社に流れる要因になります。
また、選考期間が長引くと、内定辞退やモチベーションの低下につながりやすく、結果として採用コストが上昇します。
オンライン面接や説明会の導入に加え、書類確認から内定までのフローを見直し、迅速に意思決定できる体制を整えることが、採用コスト削減への第一歩です。
採れない・辞める・コスト高…製造業採用の“三重苦”を断つ3施策
採用単価を下げるために、むやみにコストカットするだけでは逆効果です。
人材の質が下がり、結果的に定着せず早期離職や再採用が必要になることで、かえってコストが増えるケースも少なくありません。
重要なのは、効果的な施策を打ちながら「成果の出る投資」に絞り、「無駄な支出や手間」を減らしていくことです。
ここでは、製造業における採用単価の改善に直結する3つの具体策をご紹介します。
職場の情報を可視化し、早期離職を防止する
製造業では、作業内容や勤務環境に不安を抱いたまま応募する求職者も多く、入社後のギャップが離職の原因になるケースが目立ちます。
そのため、求人原稿や自社サイトにおいて「働く現場のリアル」を写真・動画・社員インタビューなどで丁寧に伝えることが、ミスマッチを防ぎ、採用コストの無駄を大きく削減できます。
選考スピードを上げて、応募者の離脱を防ぐ
複数社に同時応募が当たり前の時代。製造業においても、迅速な対応が応募者の確保につながります。
具体的には、オンライン面接の導入や選考プロセスの簡素化、即日対応できる体制の整備などが有効です。選考にかかるリードタイムを短縮することで、応募から入社までの歩留まりが改善され、効率的な採用活動に繋がります。
媒体選定を見直し、費用対効果を最大化
現在利用している求人媒体が自社の採用ターゲットに合っていない場合、いくら出稿しても成果に結びつかず、採用単価は上がる一方です。
製造業の場合、専門性の高い職種やエリア採用が多いため、業界特化型の媒体や、求職者の検索行動に合った集客力のあるサイトを活用することが効果的です。
適切な媒体選定により限られた予算でも成果が出やすくなり、費用対効果の高い採用が可能になります。
採用コストを削減したいなら、ジョブコンプラス
業種に特化した求人広告でおすすめなのが、「ジョブコンプラス」です。ジョブコンプラスは日本最大級の工場・製造業の専門求人サイトで、月間300万PVものアクセス数を誇っています。採用単価が抑えられる理由として、3つの理由が挙げられます。
【1】製造業に特化した求人設計
ジョブコンプラスは工場・製造業の仕事に特化した求人サイトです。
「工場で働きたい」「モノづくりに携わりたい」と考える求職者が集まりやすく、採用ターゲットとのマッチ度が高いことが大きな強みです。
実際のユーザー層は、20代〜30代の男性が中心で、「フォークリフト運転技能者」「アーク溶接」「クレーン運転士」「危険物取扱者」など、現場で即戦力となる資格を持った求職者も多数登録しています。
【2】WEB集客の内製化による低コスト運用
求人媒体の運用コストがかさむ原因のひとつが、外注による広告運用・集客設計です。
ジョブコンプラスでは、WEB広告運用やSEO対策を社内で一貫して行う体制を構築しています。これにより、求人市場の変化やクライアントごとのニーズに合わせて、スピーディーかつ柔軟に施策を展開できるのが強みです。
WEB集客を外注せずに内製化しているからこそ、無駄なコストをかけずに、効率的に求職者との接点を増やすことができるのです。
【3】地方もカバーする全国対応の訴求力・集客力
全国対応しているジョブコンプラスは都市部だけでなく地方や特定エリアでの人材募集にも強く、地域を問わずターゲット人材にリーチできる訴求力を持っています。
「勤務地」「職種」「給与」「勤務時間」といった基本条件に加え、「寮付き」「即入寮OK」「日払い」「未経験歓迎」「資格を活かせる」といった製造業ならではのこだわり条件でも細かく検索が可能です。
求職者が自分に合った求人にスムーズにたどり着ける検索機能の充実により、スムーズな応募を後押し。地方・郊外の採用でも、効率よく母集団形成が可能です。
これら3つの理由から、ジョブコンプラスを利用すれば、必要な職種に対して効率よく応募を集められるため、採用単価を抑えることが可能です。
ジョブコンプラスでは「サービス内容を知りたい」「採用事例が知りたい」といった採用担当者様に対して、無料相談も受け付けています。さらに、ジョブコンプラスのサイトからは資料を無料ダウンロードすることができます。
まとめ:採用単価を下げて、理想の人材と出会うには?
製造業界では慢性的な人手不足により、採用単価が高止まりする傾向があります。限られた予算の中で理想の人材を確保するには、やみくもに求人を出すのではなく、的確にターゲットへ届く打ち手が必要です。
その鍵となるのが「製造業に特化した求人広告」の活用です。製造業は職種や資格条件が細かく分かれており、汎用的な求人媒体では経験者や資格保有者の母集団形成が難しい場合もあります。結果として無駄な掲載が増え、採用単価(求人広告比費用)が膨らむリスクも。
そこでおすすめしたいのが、製造業専門の求人サイト「ジョブコンプラス」。製造職の経験者や有資格者が集まりやすく、無駄なくターゲット層へ届くため、母集団形成の効率化と採用単価の引き下げが期待できます。
コストを抑えて、欲しい人材としっかり出会いたい――。
そんな採用課題をお持ちであれば、一度ジョブコンプラスの活用を検討してみてはいかがでしょうか